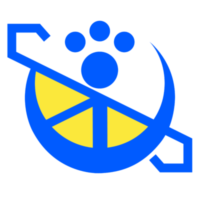子猫が段ボール箱に入れられて道端に捨てられている・・
そんな光景を、どなたでもリアルに、またはドラマや漫画で見たことがあるのではないでしょうか。
猫は避妊手術をしていないと、生涯出産回数は6~7回となります。
1回に生まれる子猫の数を3頭だとして18〜21頭、子猫の数が6頭だったとして36〜42頭となりますね。
捨て猫が数匹いたら、どんどん数が増えるのはわかりますね・・。
捨て猫を拾ったり保護したらどうしたらいいのか。
また、保健所や保護施設では猫を引き取る際、どんな対応をしているのかをみていこうかと思います!
スポンサードリンク
目次
捨て猫を拾ったらどんな対応をしたらいい?

- 近くに母猫がいないかを確認する
見つけた猫が子猫だった場合、近くに親猫がいないかを確認しましょう。
子猫を親猫が1匹ずつ口でくわえて移動させている途中の場合があります。
- 迷い猫ではないかを確認する
室内飼いの猫が脱走してしまって迷ってしまったり、迷い猫ではないか首輪や名前札をつけていないかを確認しましょう。
最近では、迷子対策としてマイクロチップを埋め込んでいる場合もあります。
近隣に「探し猫」のポスター等がないか確認し、動物病院や保健所に問い合わせがなかったか、地元の保護団体などに迷い猫として挙がっていないかを確認してみてください。
SNSなどを使用するのも良いでしょう。
また、ボランティアの保護団体がお世話をしている猫ではないかなどを確認する必要もあります。
私が飼っていた猫も、近所の猫との間に子猫を4匹産みました。
定期的に自分たちのいる場所を変えるので、1匹ずつ子猫を加えて場所を移動しているのを見たことがあります。
その時に、最後に残った1匹が例えば捨て猫だと思われて誰かに拾われていたと思うと悲しいので、拾うときは慎重にならないといけないな、と私も思いました。
スポンサードリンク
捨て猫を保護した場合は?

- 保温する
子猫の場合、体力も免疫力もまだないのですぐに体を温める必要があります。
子猫は体温調節がまだ発達していないため、箱の中に湯たんぽやカイロ、温かいと感じる程度のお湯を入れたペットボトルなどを置いて、上から毛布などを重ねた居心地のいい場所を作ってあげるとよいでしょう。
30度くらいの気温が子猫にとって最適な温度です。
- 食事を与える
成長段階に合わせて適切なエサの種類と量が必要です。
必ず猫用のミルクやキャットフードを用意しましょう。
月齢1~2か月以内なら子猫用ミルク、それ以上ならドライフードやウェットフードを与えます。
今は、コンビニでも取り扱いがあります。
- 動物病院で健康状態をチェック
もともと飼い猫だった猫が不衛生な場所に捨てられ、栄養状態も悪い状態で生活することを強いられた場合に心配なのが、感染症です。
すぐに症状が現れない感染症は、検査をしないと感染しているかどうかわかりません。
一見元気な猫に見えても、検査は必要です。
その猫の健康状態を改善する目的はもちろんですが、すでに猫を飼っている家庭で感染症を患った猫を飼い始めると、先住猫に病気がうつってしまうこともあります。
- 里親探し
保護した猫の飼い主になってくれる里親を探すには、身近な知り合い、ご近所に声をかける、里親募集サイトやSNSで希望者を見つける、といった方法があります。
今は、保護施設なども多くあるのでそういったところにコンタクトをとり相談してみるのが、もっともいい方法と考えられます。
保護団体では里親希望者に定期的に譲渡会などを開催しています。
私はこれまで何匹も捨て猫に遭遇して拾ったことがあります。
その中の1匹は雨の中の駐車場、小さな小さな猫がやせ細りフラフラと歩いていて、放っておくこと
はとてもできませんでした。
近くに親がいる気配もなかったので家に連れて帰りました。
ガタガタ震えて、何も飲まず食わずでしたが、なんとか数日かけて猫用のミルクを飲んでもらい、
少しずつ元気になりました。
牛乳は猫は飲みませんし、飲んでもお腹をこわしてしまうので気を付けましょう。
スポンサードリンク
保健所の役割「捨て猫の引き取り」とは・・?

そもそも保健所とは・・
地域住民の健康や衛生を支える公的機関の一つであり、地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市、その他指定された市(保健所政令市)、特別区(東京23区)が設置されたものです。
出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80
保健所での数ある業務の中の一つに「動物愛護」が存在し、これがいわゆる飼い主がいなくなった動物(捨て猫)や引き取り手のいない動物を預かる・保護する役割を担っています。
- 保護した動物の去勢・避妊手術など。(自治体によって異なる)
- 最終的に引き取り手が見つからなかった動物を殺処分にする。
- 民間やボランティアが運営する保護施設と連携して、里親を探す。
殺処分を減らす目的として、保健所で里親を探すことは、動物愛護管理法でも定められています。
動物の愛護及び管理に関する法律
(犬及び猫の引取り) 第三十五条
4 都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。
次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348AC1000000105
保健所のイメージは殺処分、という暗いものと以前まで私は思っていました。
しかし保健所も受入れできる数が限られていので、できるだけ殺処分をしないようにしたい、という取組みをしていることを知り、動物を飼おう、と思ったときはまず保健所などに保護されている動物を見てみてもいいのかな、と思います。
スポンサードリンク
保護施設では引き取った捨て猫にどんなことをするの??

もしも、捨て猫を見つけた場合は、保健所ではなく保護施設に連れて行くのもいいでしょう。
今は保護施設も増えているので、SNSやネットで調べるとたくさん出てきます。
しかし、保護施設によっては、環境が悪いところもあるようなのでしっかりと調べて行く必要があります。
保護施設で、猫を保護した後は主な作業内容として、次のことを行う保護施設が多いです。(保護施設により異なります)
保護施設では、新しい飼い主さんに引き渡すために必要なことをやってくれています。
- 猫のエサやり
- 猫のトイレ掃除
- 猫の爪切り、シャンプー、ブラッシング
- 病気の猫の通院やワクチン
- 避妊・去勢手術
保護した猫はいろいろな性格の子がいます。人馴れしていないため、触ることもできないどころか人間に対して威嚇して餌をまったく食べないような猫もいます。
反対に人に馴れていて甘えてくる子がいたり、中には他の猫とケンカばかりするような子もいます。
保護施設の職員はこのようなさまざまな性格をした猫に合わせて対応を変えることも必要です。
私の知り合いも、猫の保護施設を運営しています。
保護したての猫はたいてい、人間を怖がるのでシャーシャー威嚇し、猫パンチが飛んできます。
そのような猫をならすのは根気と愛情が必要です。
猫にとって住みやすい環境を作るとともに、人は怖くない存在だと分かってもらい、人を好きになってもらうことも大切な仕事です。
そして、保護施設での一番大切な役割が、譲渡会を開き里親を見つけることです。
譲渡会は定期的に会場を借りたり、保護施設内で開催し、里親希望者を募ります。
一度、飼い主と離れてしまった捨て猫が、新たな飼い主と幸せな生活を送れるようにする手伝いをするのが保護施設の大きな役割です。
私が今飼っている猫も保護猫ですが、とても幸せそうに暮らしてくれいます。
それは、これまで接してきた人たちの愛情が猫に伝わったからなのだろうと思います。
捨て猫だった時の記憶はなくなっているのではないかな、と思う日々を猫と送っています。
スポンサードリンク
まとめ
今回は、たまーに見かける捨て猫を見つけてしまった時、どうしたらいいのか?!の対応と保健所と保護施設の役割を具体的に見ていきました。
保護するか、できるかは、その時の状況によって違うと思いますので、保護をどうしてもしなくてならない、というわけではありません。
私も以前、友人宅にいた時に、庭で小さな子猫を見つけました。
でも、とても小さく目も開いていなかったので、もしかしたら親猫が近くにいるかもしれない、と思い友人と相談をしてしばらくはそのままにしておくことにしました。
しばらくして見てみたらいなくなっていたので、おそらく親猫が連れていったのだろう、と思います。
ですので、その場の状況で、保護をしなくてならない、というときは保健所や保護施設に引き取ってもらうといいでしょう。
また、今はネットやSNSで情報が多くすぐに調べる事ができますので、情報を調べてからどこに保護するかを決めるといいでしょう。