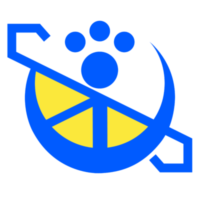ベンガルは、イエネコとヤマネコの交配によって誕生した品種で、それぞれの特徴を残しつつ今の魅力いっぱいの猫になりました。
そこで、今回はそんな魅力いっぱいのベンガルの飼い方についてみていきます。
運動量が激しい、けれど静かな場所が好きというベンガルはどのような飼育環境が好ましいのでしょうか??
スポンサードリンク
目次
ベンガルは一人暮らしで飼育可能?

ベンガルが普通の猫より運動量が多いのは有名ですよね。
そんな元気いっぱいのベンガルは一人暮らしで飼育可能なのでしょうか?
実際に飼育した人の声を参考にみていきます。
ベンガルを飼うには何よりも広いスペースが必要です!
運動量が多いので、最低でも6畳ぐらいのスペースをいつでも自由に移動できる空間は欲しいです。
広いスペースがないと、思うように運動ができないのでそれがストレスになる原因もあります。活発的でよく動き回り、じっとしていることが少ない猫です。
ベンガルを飼育するならキャットタワーも必要になってきます。ベンガルは高いところも大好きです。そのため高いところに好んで上ります。
高いところだからこそ安心してストレスなく安らげたりします。
また、静かな場所を好むので安心して過ごせる隠れ家的な、小さく狭い空間も必須です。
ですので、ワンルームのマンションやアパートのは不向きといえます。
広めの部屋で飼育することをお勧めします。高いところが好きなのでベンガルは人間の肩や背中などにも平気で飛びついて登ってきます。
ワンルームでも飼育できなくはないのですが、狭くて窮屈な部屋にベンガル自体が、ストレスを感じてくるのであまりお勧めはしません。
一人暮らしでもベンガルは飼育可能ですが、ワンルームなどは避け、ベンガルが遊べるスペースを持てる部屋だといいですね。
そのような部屋でないと、狭いところでベンガルが暴れてしまい飼い主もストレスをためることになってしまいますし、運動不足になるとベンガルがストレスにより皮膚疾患や脱毛を発症したり、攻撃的になったりしてしまう場合もあります。
スポンサードリンク
飼育に必要な用具や環境は?

いざベンガルを家に迎え入れると決まったら、いろいろと準備が必要ですね。
ここでは、何を用意したらいいのか、どのような環境を準備したいいのかを具体的にみていきます。
ベンガルとの楽しい暮らしができるよう、準備したいですね!
<必要な用具>
・猫用のトイレとトイレ砂
迎えたその日から排泄はするので、トイレグッズは必須と言えます。
猫によって好みがあるので、どれが良いかは使いながら変更していっても良いと思います。
・食器
飼育で必要な食器は、「キャットフード用」「水飲み用」の2種類です。
プラスチックやステンレス、陶器などの素材があり、それぞれ洗いやすさや扱いやすさが異なります。
アクティブに動くベンガルは、ぶつかってお皿をひっくり返すこともあります。
重みで安定した素材を選ぶと、安心です。
・ケージとキャリーバッグ
子猫の場合や、新しい環境に慣れるまではケージが安全な場所だと覚えてもらう必要があります。
2段、3段と高さのあるケージなら、トイレやベッドを置くだけでなく、猫の上下運動の欲求も満たせます。
キャリーバッグは、通院などに必ず入れることになるので、子猫の間から慣れてもらっておくと良いですよ。
・餌
餌は、ペットショップから迎える場合は、おすすめを聞いておきましょう。
最初のうちに好みがきまらない場合は、少しずつ変えていくといいでしょう。
<環境>
・広くて動きやすい環境
ベンガルは走り回ったり、高い所に上がったりするのが大好きな猫です。
「仕事で留守がちだけど猫を飼いたい」というケースでは、ベンガルのお世話時間が少なくなり、環境としては不向きと言えるでしょう。
少しお留守番の時間がある場合、ベンガルだけで遊べるキャットタワーなどを設置してあげるようにしましょう。
好奇心旺盛な性格を満たすために、おもちゃも用意してあげるといいですね。
ベンガルは、自由奔放に動き回りますが、その土台にあるのが「リラックスできる環境だから」という安心感です。
飼い主とのコミュニケーションを密に取れて、ベンガルが安心できる環境がおすすめです。
・室内飼いにする
ベンガルに限ったことではないですが、事故や感染症にかかるリスクから、室内飼いが長生きの秘訣と言われています。
家の中を自由に移動できるように、昼間はできるだけ部屋の戸を解放し、できれば猫専用の出入り口を作りましょう。
ベンガルは走り回ったり、高い所に上がったりするのが大好きな猫です。そうした性格から、狭い部屋やケージに閉じ込めると強いストレスを感じてしまいます。
野生的なベンガルは猫の中でも特に縄張り意識が強く、室内で暮らしていても家中をパトロールしないと気がすみません。
「どうして用もないのに入りたがるのかな?」と不思議に思うかもしれませんが、使わない部屋であっても自由に出入りできるようにしましょう。
・自由に爪をとげる場所を用意する
野生的なベンガルは所構わずに爪とぎをして、壁紙や柱をボロボロにすることがあります。そこで、猫の動線上に爪とぎグッズを複数配置して、気が向いたときに自由に爪とぎできる場所を用意してあげてください。
スポンサードリンク
ベンガルのお迎え時はいつ頃?一ヶ月~一年の体重推移と飼育費用!

ベンガルを家にお迎えしたいけれどいつごろがいいのか、普通の猫より運動量が多いけどどれくらいの体重の変化があるのかな?
などの、疑問点を深ぼりしていきます。
迎え入れるベンガルの成長をあらかじめ知っておくことで、飼い主の心の準備や具体的に準備しなくてはいけないことがみえてくるでしょう。
◆子猫期
・生後1ヶ月
人間でいう2歳くらいのこの時期の体重は、350g~500gくらいといわれています。
ペットショップではあまり見かけることも少ないかもしれませんが、大体500mlのペットボトル1本分くらいです。
この時期は子猫用ミルクを与えます。
・生後2ヶ月
他の猫種とはさほど変わりなく、700g~1㎏くらいまで成長します。
人間でいうと大体3歳児くらいです。
子猫用ミルク、子猫用フードなどを与えます。
・生後3ヶ月
平均体重は大体1~1.5㎏くらいで、この頃からぐんぐんと大きくなり、成長していきます。
一般的にベンガルの子猫を家族に迎えるのは生後3か月前後です。
生後3ヶ月くらいまでは他の猫と同じくらいの成長です。
・生後6ヶ月
生後5ヶ月を過ぎると体重は2㎏を超え、この頃にはぐんと大きくなって体重は3㎏近くなります。
3ヶ月~6ヶ月がピークとされており目に見えて成長が分かるでしょう。
全年齢用フードを与え始めます。
・生後8~12ヶ月
人間でいうと大体18歳くらいで、体重は3.5~4.5㎏くらいになります。
ベンガルは生後1年を過ぎてもゆるやかに成長しますので、ここから他の猫との差が出てきます。
オスの方が一回り大きく育ちやすいので、1歳を過ぎても成長を続け、たくましいボディへと育つでしょう。
◆成猫期
成猫は、1歳になった頃から7歳になるまでの時期を指します。
ベンガルは1年から1年半かけて成長するため、体をつくる重要な時期です。
成猫期に入ってから1歳半くらいまではゆるやかに成長するので一般より大きくなるのはここからです。
オスの平均体重で4~7㎏、メスで3~5㎏くらいです。
成長スピードには個体差があるので必ずしも平均体重になるとは限りません。
成猫用フードを1日2回に分けて与えます。
◇飼育費用
ベンガルは運動量が多い活発な猫種ということもあり、そのほかの猫種と比べて消費カロリーが多くなる傾向があります。
一般的な成猫のサイズが3〜5kgくらいなのに対して、ベンガル(オス)のサイズが5〜8kgくらいということも踏まえると、一般的なサイズの猫の1.5〜2倍くらいの餌代がかかると思っておくのがいいでしょう。
キャットフードはものによって値段がマチマチであるため、一概にいくらかかると言い切るのは難しいですし、猫の運動量や体格によって、与える量や回数にも差が出てきます。
目安として餌代は1ヶ月で3000円から4000円とみるといいでしょう。
運動量が多くて活発な猫種であるベンガルには、良質な肉原材料が主原料として使われている高タンパク・低炭水化物・高脂質なフードがおすすめです。
私も猫を飼っていますが、毎日の餌代の他にも消耗品として、トイレの砂、ペットシーツ、消臭剤、猫のおもちゃなど、またワクチンや旅行に行く際のペットホテル代などもかかってきます。
スポンサードリンク
ベンガルが注意するべき病気とは?

・ピルビン酸キナーゼ欠損症
「ピルビン酸キナーゼ欠損症」は、赤血球に存在するピルビン酸キナーゼという酵素が先天的に欠損することで、十分なエネルギーの産生ができなくなり、赤血球の寿命が短くなる疾患です。
血管内で赤血球が壊れていくので、症状として慢性的な貧血、耳や歯茎と言った可視粘膜の蒼白、すぐに疲れる、呼吸が速いといったものが見られます。
遺伝性疾患なので予防法は確立されていません。しかし、環境やストレスが発症の要因となっている可能性が報告されています。
運動不足を解消してストレスを軽減することが予防につながるかもしれません。
・進行性網膜委縮
進行性網膜委縮は、目の中にある網膜が変性・委縮することにより視力が低下する病気です。
視力低下は少しずつ進み、最終的には失明してしまいます。
症状は、まずは夜間に見えづらい(夜盲)が現れます。進行してくると、日中でも目が見えなくなり、夜間と同様の視力の低下が起こります。
進行性網膜萎縮の予防法や治療は確立されていません。しかし、命にかかわる疾患ではなく、徐々に進行する病気であるため、愛猫のベンガルがかかったとしても、家具の位置を覚えている室内などでは元気に過ごす子は多いと言えます。視力低下の兆候が確認したら、生活環境をできるだけ変えずに生活してあげましょう。
・子宮蓄膿症
子宮蓄膿症とは、メス猫の子宮内に病原体が入り込み、炎症反応が起こって膿が溜まってしまう病気です。
治療では抗生物質の投与が行われ、場合によっては外科的に子宮を摘出する場合もあります。
・猫伝染性腹膜炎(FIP)
猫腸コロナウイルスが突然変異を起こして強い病原性を獲得し、腹膜炎を特徴とする激しい症状を引き起こす致死性の高い病気。
ひとたび発症してしまうと効果的な治療法がなく、二次感染を防ぐための抗生物質の投与、免疫力を高めるためのネコインターフェロンの投与、炎症を抑えるための抗炎症薬の投与などで様子を見るというのが基本方針です。
・白内障
白内障とは、眼球内にある水晶体と呼ばれる組織が白く濁り、視力が低下~喪失してしまった状態のこと。
糖尿病や低カルシウム結晶、ブドウ膜炎など、他の病気がきっかけで発症することもあります。
症状の軽減を目的とした対処療法が主で、場合によっては外科手術が行われることもあります。
ベンガルは、基本的に感染症への抵抗が高い猫種と言われていますが、いくつかかかりやすい遺伝性疾患があります。
また、好奇心の強い性格、活発な性格上けがや誤飲はほかの猫種と比較してかなり多いと言えます。
飼い主が気を付けてベンガルを育ててあげるといいでしょう。
スポンサードリンク
まとめ
運動量が普通の猫よりも多く、甘えん坊なため飼い主と遊ぶ時間を必要とするベンガルを飼うには、それなりに広いスペースとベンガルとのコミュニケーションを取る時間をもつことが必要なことがわかりました。
1人暮らしでも飼育は可能ですが、走り回ったりするので犬並みの騒音がすることなどを考えると、一人暮らしでもアパートなどよりは一戸建ての方が適しているかもしれませんね。
他の猫種に比べると、体も大きくなりますしその分餌も多く食べます。
飼育環境や注意するべき病気について、飼い主がきちんと認識したうえで、ベンガルをお迎えするといいでしょう。